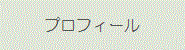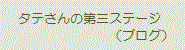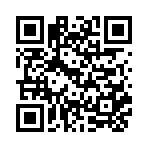2011年12月28日
エントリーシート
2013年卒業生の就職活動が12月に解禁となりました。今は各社に提出するエントリーシートの作成に追われている頃かと思います。
特に現状の様な狭き門では、第一次選考、ふるい落としの傾向が強くなりますので、無視できません。また、資質や能力の他文章力なども見られますので、十分に吟味することが大切です。
ポイントは3つです。自分を知り(自己分析)、相手を知り(企業研究)、そして両者をつなぐコミュニケーション(文章力)を磨くこと。
この中では、やはり自己分析が一番難しいでしょうね。自己PR、長所・短所、学生時代に力を注いだこと、挫折を乗り越えたこと、そして志望理由など。どれをとっても自己分析が関係してきます。
ただ単に事柄を述べるのではなく、そうした事柄に沿って具体的に、自分はどんなことを感じたのか、あるいは何を学んだのか、どんな行動を取ったのか、そして、今後どう活かしたいのかなどをアッピールしたいですね。
学生さんとお話していると、なかなか自分の良さが分からない方がいらっしゃいます。そういう場合には、いろいろと質問させて頂き、ご自身で気づいてもらいます。
エントリーシートは面接に結びついていますから嘘があってはいけません。あくまでもご本人の認識から出発してご本人の言葉で表現できないと答えられませんからね。
企業研究は、業界地図から出発し、HPや会社四季報を活用します。また、新聞記事なども当たっておきたいですね。
ライバル企業との比較表を作り、企業の強み弱み、市場環境(機会と脅威)などを分析して、その企業でどんな仕事がしたいのか、そこまで明確に説明できれば強いですね。
コミュニケーションとしての文章力や説得力も重要です。表現方法を考えるよりもまず何を言いたいのかをはっきりさせることが先決ですね。そして、肯定的に表現することも大事です。
こうしてみると、エントリーシートを作成する段階から面接は始まっているといっても過言ではありません。面接ではどんな質問になって帰ってくるのか分かりませんので、まずは自分の興味や能力、価値観を明確にしておくことから始めるといいでしょう。
では、私からの質問です。
1)どんなことに興味がありますか?
どんなことにやりがいを感じますか?
2)どんなことが得意ですか?
どんな時に力を発揮しますか?
3)大事だと思うことはどんなことですか?
優先させたいことは何ですか?
特に現状の様な狭き門では、第一次選考、ふるい落としの傾向が強くなりますので、無視できません。また、資質や能力の他文章力なども見られますので、十分に吟味することが大切です。
ポイントは3つです。自分を知り(自己分析)、相手を知り(企業研究)、そして両者をつなぐコミュニケーション(文章力)を磨くこと。
この中では、やはり自己分析が一番難しいでしょうね。自己PR、長所・短所、学生時代に力を注いだこと、挫折を乗り越えたこと、そして志望理由など。どれをとっても自己分析が関係してきます。
ただ単に事柄を述べるのではなく、そうした事柄に沿って具体的に、自分はどんなことを感じたのか、あるいは何を学んだのか、どんな行動を取ったのか、そして、今後どう活かしたいのかなどをアッピールしたいですね。
学生さんとお話していると、なかなか自分の良さが分からない方がいらっしゃいます。そういう場合には、いろいろと質問させて頂き、ご自身で気づいてもらいます。
エントリーシートは面接に結びついていますから嘘があってはいけません。あくまでもご本人の認識から出発してご本人の言葉で表現できないと答えられませんからね。
企業研究は、業界地図から出発し、HPや会社四季報を活用します。また、新聞記事なども当たっておきたいですね。
ライバル企業との比較表を作り、企業の強み弱み、市場環境(機会と脅威)などを分析して、その企業でどんな仕事がしたいのか、そこまで明確に説明できれば強いですね。
コミュニケーションとしての文章力や説得力も重要です。表現方法を考えるよりもまず何を言いたいのかをはっきりさせることが先決ですね。そして、肯定的に表現することも大事です。
こうしてみると、エントリーシートを作成する段階から面接は始まっているといっても過言ではありません。面接ではどんな質問になって帰ってくるのか分かりませんので、まずは自分の興味や能力、価値観を明確にしておくことから始めるといいでしょう。
では、私からの質問です。
1)どんなことに興味がありますか?
どんなことにやりがいを感じますか?
2)どんなことが得意ですか?
どんな時に力を発揮しますか?
3)大事だと思うことはどんなことですか?
優先させたいことは何ですか?
2011年12月23日
口頭試問から見えるもの
第36回二次試験が12月18日(日)に終わりました。今回は直前で「判定ポイント」が変わりましたので、どんな試験になるのか注目です。その点を口頭試問からレビューしてみたいと思います。
一番多かった質問は「CDAの資格をどのように活かしますか?」だったようです。殆どすべての受験者に出された質問で、これが最後の質問という点もいつもと変わりません。具体的に、熱く語ってOKです。
また、「如何でしたか?」「感想は?」「評価したら?」「点数をつけると?」などの総括的な質問も従来通りだったようです。どんな話を聴くことが出来たのか、どんな点に共感できたのか、キーワードを使って説明できれば問題ないと思います。
それから、「出来たこと、出来なかったこと」「この後面談が続くとしたら」なども従来通り出されたと聞いています。また、「主訴」又は「主訴と来談目的」を問う質問もあったようです。
ここまでは目新しい点はありません。ですが新しい質問も2つほど見受けられました。
その1は、「クライエントについてどの様に思われましたか?」あるいは「このクライエントはどういう人だと思いますか?」です。この問いはクライエントに対する「見立て」を求めていると思われますので、来談目的や状況を中心に、主訴なども交えて答えればいいかと思います。
その2は、「クライエントの問題は何だと思いますか?」とずばり「問題」を問うものです。中には「問題」と「主訴」を別々に問われたケースもあったようですので、受験生は戸惑われたかもしれません。(「問題」については『CDA二次試験の新判定ポイント(2/2)』をご参照ください。)
こうしてみると、従来とは大きく変わらないものの、主訴や問題点といったクライエントの「見立て」を中心にした問いが目立ってきたような気がします。
これからはより傾聴に力を注ぐとともに、的確な質問力も鍛えて行かなければいけませんね。
〔CDA実践研究会〕
http://ja-jp.facebook.com/cdasupport
一番多かった質問は「CDAの資格をどのように活かしますか?」だったようです。殆どすべての受験者に出された質問で、これが最後の質問という点もいつもと変わりません。具体的に、熱く語ってOKです。
また、「如何でしたか?」「感想は?」「評価したら?」「点数をつけると?」などの総括的な質問も従来通りだったようです。どんな話を聴くことが出来たのか、どんな点に共感できたのか、キーワードを使って説明できれば問題ないと思います。
それから、「出来たこと、出来なかったこと」「この後面談が続くとしたら」なども従来通り出されたと聞いています。また、「主訴」又は「主訴と来談目的」を問う質問もあったようです。
ここまでは目新しい点はありません。ですが新しい質問も2つほど見受けられました。
その1は、「クライエントについてどの様に思われましたか?」あるいは「このクライエントはどういう人だと思いますか?」です。この問いはクライエントに対する「見立て」を求めていると思われますので、来談目的や状況を中心に、主訴なども交えて答えればいいかと思います。
その2は、「クライエントの問題は何だと思いますか?」とずばり「問題」を問うものです。中には「問題」と「主訴」を別々に問われたケースもあったようですので、受験生は戸惑われたかもしれません。(「問題」については『CDA二次試験の新判定ポイント(2/2)』をご参照ください。)
こうしてみると、従来とは大きく変わらないものの、主訴や問題点といったクライエントの「見立て」を中心にした問いが目立ってきたような気がします。
これからはより傾聴に力を注ぐとともに、的確な質問力も鍛えて行かなければいけませんね。
〔CDA実践研究会〕
http://ja-jp.facebook.com/cdasupport
2011年12月22日
コーチング・ミニミニ講座64
下記の通り開催しますので、お時間のある方はご参加ください。
【第64回コーチング・ミニミニ講座】
日時:1月 8日(日)AM10時~12時
場所:三鷹市市民協働センター
ミーティングルーム
費用:無料
(お菓子差し入れ歓迎)
特別な準備はいりません。気楽にご参加頂ければ結構です。
但し、守秘義務にご留意頂き、発言内容等の公開はご遠慮ください。
参加希望の方は、『お問い合わせ』画面からお願いします。
【第64回コーチング・ミニミニ講座】
日時:1月 8日(日)AM10時~12時
場所:三鷹市市民協働センター
ミーティングルーム
費用:無料
(お菓子差し入れ歓迎)
特別な準備はいりません。気楽にご参加頂ければ結構です。
但し、守秘義務にご留意頂き、発言内容等の公開はご遠慮ください。
参加希望の方は、『お問い合わせ』画面からお願いします。
2011年12月22日
第2回コミュニティ・コーチング講座
下記の通り、「コーチング・ミニミニ講座会員向け」にコミュニティ・コーチング講座を行います。
資格取得や難しいスキルにこだわらず、日常生活で役立つコーチングを「コミュニティ・コーチング」と名付けました。
この講座は、コーチングの初歩をやさしく学ぶ講座です。
【第2回コミュニティ・コーチング講座三鷹(全5回)】
日程:2012年
第1日 1月22日(日)
第2日 2月19日(日)
第3日 3月18日(日)
第4日 4月22日(日)
第5日 5月20日(日)
時間はいづれもAm10:00~12:00(2時間)です。
場所:三鷹市市民協働センター
対象:コーチング・ミニミニ講座会員
費用:500円/回(テキスト代等を含みます。)
ご興味のある方は「コーチング・ミニミニ講座」に一度ご参加ください。内容をご説明致します。
資格取得や難しいスキルにこだわらず、日常生活で役立つコーチングを「コミュニティ・コーチング」と名付けました。
この講座は、コーチングの初歩をやさしく学ぶ講座です。
【第2回コミュニティ・コーチング講座三鷹(全5回)】
日程:2012年
第1日 1月22日(日)
第2日 2月19日(日)
第3日 3月18日(日)
第4日 4月22日(日)
第5日 5月20日(日)
時間はいづれもAm10:00~12:00(2時間)です。
場所:三鷹市市民協働センター
対象:コーチング・ミニミニ講座会員
費用:500円/回(テキスト代等を含みます。)
ご興味のある方は「コーチング・ミニミニ講座」に一度ご参加ください。内容をご説明致します。
タグ :コミュニティ・コーチング
2011年12月08日
CDA二次試験の新判定ポイント(2/2)
第36回二次試験から適用される「新判定ポイント」の後編です。前篇では「3)傾聴(非言語表現)」「4)傾聴(言語表現)」「5)傾聴(かかわり方)」について触れました。
2)自己探索の支援
ひとは内面(環境や経験から得た自身の考え方、価値観、認識など)を見つめること=「自己探索」で成長すると思われます。しかしながら辛い経験をした場合などなかなか内面を見つめる気にはなれないものです。
そんな時、信頼できる第三者がいたら・・・。これがキャリアカウンセリングの出発点です。
さて、「自己探索の支援」とはどんなことをしたらいいのでしょう? 言うまでもなくクライエントが自己に向き合えるように働きかけることですが、分かり易くする為に「自己探索の支援を妨げること」について考えてみたいと思います。
最初に考えられるのは「問題を解決しようとすること」です。これではクライエントの自己探索を支援するどころか邪魔をしてしまいますね。成長の機会を奪うことになります。
「CDAの興味から発する質問」も自己探索の妨げになります。せっかく自己探索に集中していても、別のことについて質問されたら、自己探索を中断して質問に対する答を考えなければいけませんからね。
また、見当違いの「要約」「いいかえ」「反映」なども自己探索の妨げになります。勿論、不適切な非言語的表現なども信頼関係を損なうという点では自己探索どころではないですね。
「自己探索の支援」とはこの様に正しい形で行われる「問いかけ」や「働きかけ」(=各種支援スキル)ですが、難しいスキルを無理してやろうとせず、基本スキルを正確に使う。そして、自己探索を妨げることは絶対しない、という心掛けが大切だと思います。
1)主訴・問題の把握
さて、いよいよ最後ですね。「主訴・問題」となっています。「主訴」と「問題」、同じなのか、違うのか、違うとすればどう違うのか。
その前に、「来談目的」というのがあります。これはご相談に来られた直接的な目的で、面談の冒頭でクライエントから語られることが多いと思います。例えば「転勤で迷っている」「リストラで転職したい」などです。
「主訴」は、そうした事態に対する強い感情、情動です。それは「怒り」だったり「落胆」だったり、「焦り」だったり、「葛藤」だったり。あるいはそれらが複合したものだったりします。
では、「問題」とは何でしょう? 特にキャリアカウンセリングでいう「問題」とは?
例えば「転勤」。「それは大変ですねぇ」とはなりませんよね。そうです。ここで大事なのは「一般的価値観」の排除です。つまり、「思い込み」や「決め付け」は絶対ダメということですね。
ですから、「転勤」や「リストラ」などは「問題」とは考えません。ある人にとってはチャンスと考えてキャリアアップを図るかもしれませんからね。
「転勤」や「リストラ」は多くの場合、本人の力ではどうしようもないこと=本人の外にある「環境・条件」です。「問題」は「転勤」や「リストラ」についてのご本人の「考え方」や「価値観」「認識」(つまり、誤った自己概念や固定観念、思い込みなど)です。
いろいろな考え方が出来るのに、どうして「転勤」=(例えば)「怒り」と感じるのか? そうした「内面」に焦点を当て、自己探索を促し、自ら人生を切り開いて頂こうとするのがキャリアカウンセリングです。
ですから、キャリアカウンセリングにおける「問題」とは実に「個人的な問題」なんですね。だからこそ自己探索することに意味があり、成長につながる訳です。
「来談目的」・「主訴」・「問題」を区分してみると、クライエントの心理構造についての理解がし易くなります。従って、何について「要約」したらいいのか、何について「質問」や「反映」をしたらいいのか、自然に見えてくるような気がします。
以上が「新判定ポイント」についての私の”個人的な”見方です。
私自身、「新判定ポイント」に向き合ってみて大変勉強になりました。
こうしてみると、JCDAの提唱する『経験代謝』がこの「新判定ポイント」の先に何となく浮かんで見えますが、二次試験の10分間ではそこまで出来ませんので、深く考えすぎないでくださいね。
〔CDA実践研究会〕
http://ja-jp.facebook.com/cdasupport
2)自己探索の支援
ひとは内面(環境や経験から得た自身の考え方、価値観、認識など)を見つめること=「自己探索」で成長すると思われます。しかしながら辛い経験をした場合などなかなか内面を見つめる気にはなれないものです。
そんな時、信頼できる第三者がいたら・・・。これがキャリアカウンセリングの出発点です。
さて、「自己探索の支援」とはどんなことをしたらいいのでしょう? 言うまでもなくクライエントが自己に向き合えるように働きかけることですが、分かり易くする為に「自己探索の支援を妨げること」について考えてみたいと思います。
最初に考えられるのは「問題を解決しようとすること」です。これではクライエントの自己探索を支援するどころか邪魔をしてしまいますね。成長の機会を奪うことになります。
「CDAの興味から発する質問」も自己探索の妨げになります。せっかく自己探索に集中していても、別のことについて質問されたら、自己探索を中断して質問に対する答を考えなければいけませんからね。
また、見当違いの「要約」「いいかえ」「反映」なども自己探索の妨げになります。勿論、不適切な非言語的表現なども信頼関係を損なうという点では自己探索どころではないですね。
「自己探索の支援」とはこの様に正しい形で行われる「問いかけ」や「働きかけ」(=各種支援スキル)ですが、難しいスキルを無理してやろうとせず、基本スキルを正確に使う。そして、自己探索を妨げることは絶対しない、という心掛けが大切だと思います。
1)主訴・問題の把握
さて、いよいよ最後ですね。「主訴・問題」となっています。「主訴」と「問題」、同じなのか、違うのか、違うとすればどう違うのか。
その前に、「来談目的」というのがあります。これはご相談に来られた直接的な目的で、面談の冒頭でクライエントから語られることが多いと思います。例えば「転勤で迷っている」「リストラで転職したい」などです。
「主訴」は、そうした事態に対する強い感情、情動です。それは「怒り」だったり「落胆」だったり、「焦り」だったり、「葛藤」だったり。あるいはそれらが複合したものだったりします。
では、「問題」とは何でしょう? 特にキャリアカウンセリングでいう「問題」とは?
例えば「転勤」。「それは大変ですねぇ」とはなりませんよね。そうです。ここで大事なのは「一般的価値観」の排除です。つまり、「思い込み」や「決め付け」は絶対ダメということですね。
ですから、「転勤」や「リストラ」などは「問題」とは考えません。ある人にとってはチャンスと考えてキャリアアップを図るかもしれませんからね。
「転勤」や「リストラ」は多くの場合、本人の力ではどうしようもないこと=本人の外にある「環境・条件」です。「問題」は「転勤」や「リストラ」についてのご本人の「考え方」や「価値観」「認識」(つまり、誤った自己概念や固定観念、思い込みなど)です。
いろいろな考え方が出来るのに、どうして「転勤」=(例えば)「怒り」と感じるのか? そうした「内面」に焦点を当て、自己探索を促し、自ら人生を切り開いて頂こうとするのがキャリアカウンセリングです。
ですから、キャリアカウンセリングにおける「問題」とは実に「個人的な問題」なんですね。だからこそ自己探索することに意味があり、成長につながる訳です。
「来談目的」・「主訴」・「問題」を区分してみると、クライエントの心理構造についての理解がし易くなります。従って、何について「要約」したらいいのか、何について「質問」や「反映」をしたらいいのか、自然に見えてくるような気がします。
以上が「新判定ポイント」についての私の”個人的な”見方です。
私自身、「新判定ポイント」に向き合ってみて大変勉強になりました。
こうしてみると、JCDAの提唱する『経験代謝』がこの「新判定ポイント」の先に何となく浮かんで見えますが、二次試験の10分間ではそこまで出来ませんので、深く考えすぎないでくださいね。
〔CDA実践研究会〕
http://ja-jp.facebook.com/cdasupport
2011年12月05日
CDA二次試験の「新判定ポイント」(1/2)
第36回の二次試験から「判定ポイント」が変わりましたね。
従来の判定ポイントは
「傾聴スキルを使い、信頼関係の構築を図るとともにクライエントのニーズや状況を確認すること」でした。
それが、今回から下記のようになっています。
1)主訴・問題の把握
2)自己探索の支援
3)傾聴(非言語表現)
4)傾聴(言語表現)
5)傾聴(かかわり方)
どうでしょう? 直前の変更は不安ですよね。ですが、直前だからこそ大きな変化はないと肯定的にとらえてみたらどうでしょう。但し、押さえるところはしっかり押さえて。
5つの項目の内3つが「傾聴」ですね。それだけ「傾聴」を重視している訳です。従って「傾聴」が出来なかったらアウト!ということになってしまいます。
3)傾聴(非言語表現)
これは「かかわり行動」の非言語的な部分、つまり「視線」「身体言語」「声の調子」を指すと考えていいでしょう。従来から「CDA実践研究会」ではこの3つを重視してきましたので、基準がはっきりして良かったと思います。
基礎中の基礎であるこれら3つのツールですが、しっかり出来ている受験生はほんの一握りです。殆どの方は自己流、自己満足だけでクライエントとの関係が意識されていないんですね。残された時間をこの3つの実践に特化するだけでもカウンセリングらしい場になってくると思います。
4)傾聴(言語表現)
これは「かかわり行動」の言語的な部分、「言語的追跡」がメインになります。「サクセス・ポイント(4)」にも書きましたが、CDAから話題を変えたり、話を飛躍させてはいけない、つまりクライエントの話を”後からついていく”感じで集中するということですね。
ですから、何を言うべきかを考えたり話の先回りをすることは厳禁なんですね。「質問」にしても「要約」や「いいかえ」にしても原則は「言語的追跡」ですので、しっかり身に付けておくことが大切です。
5)傾聴(かかわり方)
傾聴の最後、3つ目は「かかわり方」つまり「CDA側の姿勢」です。クライエントを非言語・言語の両面から観察し、支持的・肯定的に、クライエントに合わせて柔軟にかかわることがポイントです。そうすることで「話し易い場」ができるんですね。
また、ロージャーズの流れをくむ「パーソン・センタード・アプローチ」も参考になると思います。つまり、「自己一致/純粋性」「無条件の肯定的尊重/非審判的態度/受容」そして「共感的理解」ですね。
こうした総合的傾聴によって、はじめて「2)自己探索の支援」が可能になってくる訳です。
(続く)
2/2では、1)主訴・問題の把握、2)自己探索の支援、について触れたいと思います。
従来の判定ポイントは
「傾聴スキルを使い、信頼関係の構築を図るとともにクライエントのニーズや状況を確認すること」でした。
それが、今回から下記のようになっています。
1)主訴・問題の把握
2)自己探索の支援
3)傾聴(非言語表現)
4)傾聴(言語表現)
5)傾聴(かかわり方)
どうでしょう? 直前の変更は不安ですよね。ですが、直前だからこそ大きな変化はないと肯定的にとらえてみたらどうでしょう。但し、押さえるところはしっかり押さえて。
5つの項目の内3つが「傾聴」ですね。それだけ「傾聴」を重視している訳です。従って「傾聴」が出来なかったらアウト!ということになってしまいます。
3)傾聴(非言語表現)
これは「かかわり行動」の非言語的な部分、つまり「視線」「身体言語」「声の調子」を指すと考えていいでしょう。従来から「CDA実践研究会」ではこの3つを重視してきましたので、基準がはっきりして良かったと思います。
基礎中の基礎であるこれら3つのツールですが、しっかり出来ている受験生はほんの一握りです。殆どの方は自己流、自己満足だけでクライエントとの関係が意識されていないんですね。残された時間をこの3つの実践に特化するだけでもカウンセリングらしい場になってくると思います。
4)傾聴(言語表現)
これは「かかわり行動」の言語的な部分、「言語的追跡」がメインになります。「サクセス・ポイント(4)」にも書きましたが、CDAから話題を変えたり、話を飛躍させてはいけない、つまりクライエントの話を”後からついていく”感じで集中するということですね。
ですから、何を言うべきかを考えたり話の先回りをすることは厳禁なんですね。「質問」にしても「要約」や「いいかえ」にしても原則は「言語的追跡」ですので、しっかり身に付けておくことが大切です。
5)傾聴(かかわり方)
傾聴の最後、3つ目は「かかわり方」つまり「CDA側の姿勢」です。クライエントを非言語・言語の両面から観察し、支持的・肯定的に、クライエントに合わせて柔軟にかかわることがポイントです。そうすることで「話し易い場」ができるんですね。
また、ロージャーズの流れをくむ「パーソン・センタード・アプローチ」も参考になると思います。つまり、「自己一致/純粋性」「無条件の肯定的尊重/非審判的態度/受容」そして「共感的理解」ですね。
こうした総合的傾聴によって、はじめて「2)自己探索の支援」が可能になってくる訳です。
(続く)
2/2では、1)主訴・問題の把握、2)自己探索の支援、について触れたいと思います。